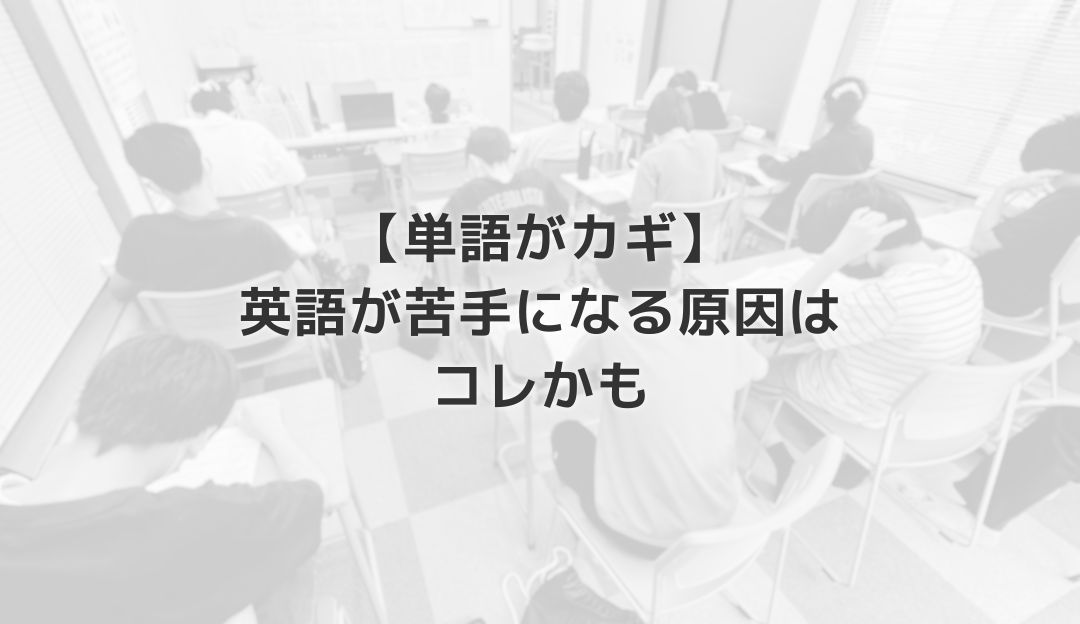やっぱり中学校の英語の教科書は、昔に比べて難しくなっていると思う。
特に気になるのが、出てくる単語のレベル。
たとえば中学2年の教科書には「breathtaking」という単語が出てくる。
ぱっと見たら「何これ」と感じるかもしれないけど、よく見ると「breath(息)」と「take(取る)」に分けられる。
直訳すると「息を取るような」、つまり「息を呑むほどの」「すごい」という意味になる。
そう考えると少しわかりやすくなるね。
でも、そんなふうに冷静に分析できるのは、ある程度余裕がある子だけだ。
英語が苦手な子がいきなりこの単語を見たら、「なんだこれ」で終わってしまうかもしれない。
僕が中学生だったころ、こんな単語は教科書に出てこなかった気がする。
もっとシンプルで、使いやすい英語が中心だった。
「This is a pen」まではいかないけど、少なくとも「breathtaking」なんて、ちょっとおしゃれな表現は見なかった。
でも今の教科書では、こういう単語がさらっと出てくる。
ただ、そのぶん「単語を覚えているかどうか」で、英語が好きになるか嫌いになるかが決まってしまう気がする。
そもそも、知らない単語がずらっと並んでいる教科書を見て「わあ、おもしろそう!」と思える中学生はそう多くない。
というか、そんな子はいないだろう。
やっぱり読めるからこそ意味がわかって、意味がわかるから楽しくなる。
その順番が逆になることは、なかなかない。
だからこそ、英語が苦手な子には「フォニックス」から入り口を丁寧につくってあげたい。
いきなり難しい単語が並ぶ教科書に飛び込むのではなく、まずは「英語が読める・わかる」という体験を積み重ねること。
そこが、英語嫌いを防ぐ一番の近道だと思う。
サクセス未来塾
にっさい花みず木校
中村