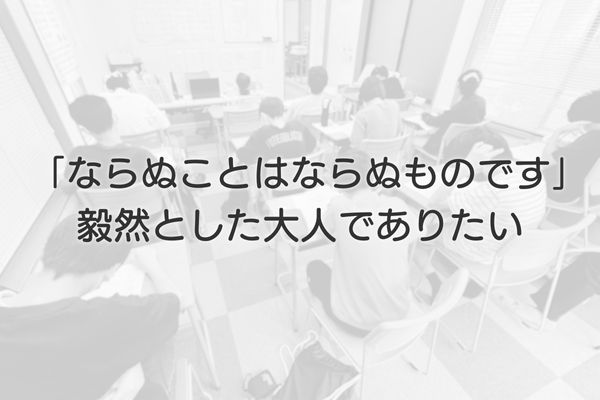会津藩では
6歳から9歳の藩士の子どもたちが十人ほど集まり
「什(じゅう)」というグループを作っていた。
そこでは年長者が「什長(リーダー)」を務め
毎日順番に誰かの家に集まり
こんな教えを説いたそうだ。
一、年長者(としうえのひと)の言ふことに背いてはなりませぬ
一、年長者にはお辞儀をしなければなりませぬ
一、嘘言(うそ)を言ふことはなりませぬ
一、卑怯な振舞をしてはなりませぬ
一、弱い者をいぢめてはなりませぬ
一、戸外で物を食べてはなりませぬ
一、戸外で婦人(おんな)と言葉を交へてはなりませぬ
そして最後に付け加えられるのが
「ならぬことはならぬものです」
これが「什の掟」と呼ばれるものだ。
興味深いのは
この「什の掟」は大人から一方的に押し付けられたわけではなく
当時の子どもたち自身が取り決め互いに守り合っていたといわれている点だ。
年長者といっても
小学校低学年から中学年ほどの年齢でありながら
自分たちのリーダーを立て
きちんとルールを決め
違反したときには戒め合った。
いまの時代に生きる子どもたちにとっては
ここまで厳しく自分たちを律するのは難しいかもね。
「ならぬことはならぬものです」
つまり
「ダメなものはダメ」
ということ。
いまの教育現場には
このシンプルで強い言葉が必要だと思う。
今は「多様性」や「自主性」が重視され
何でも自由に振る舞ってよいかのような風潮が広がっている。
しかし
多様性を尊重し一人ひとりの自主性を育むことが大切だとしても
何がなんでも許されるわけではない。
学校では「なんでダメなんだ」「理由を説明しろ」「理不尽だ」と
先生に強く反発する子がいると聞く。
たしかに「ダメな理由」をきちんと説明されなければ
納得できないのは当然かもしれない。
しかし
集団生活の中で最低限守るべきことは必ず存在する。
「なんで?」と言われるたびに何もかも許していては
集団としての秩序は成り立たない。
そして
今は昔と比べて先生が子どもを叱りにくい社会になった。
ちょっと厳しいことを言えば保護者からクレームが入ったり
子どもたちも「先生は何もできない」と分かっているから
先生に対して失礼な態度を取ったりと…
もう完全に大人が子どもに舐められてしまっているんだ。
もちろん
大人が一方的に考えを押し付けるのではなく
子どもの立場になって対話する姿勢を持つことはとても大切だ。
これは間違いない。
対話によって子ども自身が納得し
自分の行動を振り返ってくれれば理想的だ。
それでも僕は
最終手段として「ならぬことはならぬものです」と言える覚悟を持っておきたい。
どれだけ対話を尽くしても守るべきラインがあるなら
大人が「ダメなものはダメだ」とはっきり伝えなくちゃいけない。
多様性の時代だからこそ
子どもから舐められない強い大人でありたいと思う。
サクセス未来塾
にっさい花みず木校
中村